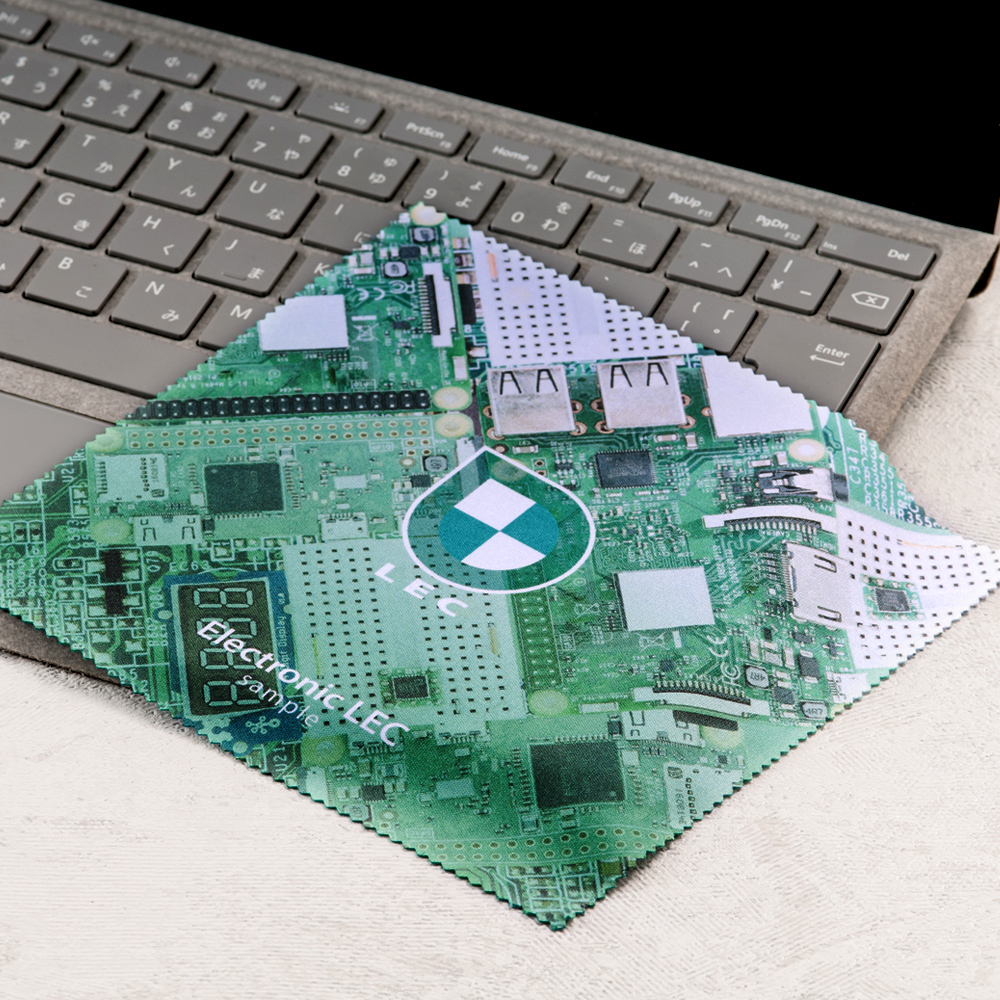〇「RGB」の見た目が「CMYK」では反映されないのはどうして?
2025.05.13
おさらいになりますが、一般的に販促品・ノベルティ作りの流れは、まず目的やターゲットに沿ったアイテムを決定、その後にパソコンでデザインを行います。
完成した原稿は印刷所に入校後、印刷機によって、アイテムにプリントが施されます。
この時、原稿のカラーモードは「RGB」で、パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンを利用しても同じモードになります。
次に印刷所へ入稿しますが、ここで何もしないままだと、データは「RGB」のままです。
一方、印刷機のカラーモードは「CMYK」で、入稿原稿とは異なります。
この場合、印刷所では、「原稿の差し戻し」「RGBに設定されたカラーモードをCMYKに変換」といった対応をします。差し戻しの場合、「カラーモードを「CMYK」に変換して入稿してください」といわれることが多いようです。
なお、RGBに対応した印刷機を採用しているのであれば、そのまま印刷が行われます。
※弊社では、RGB対応の印刷機は採用しておりません。
このことから、原稿のカラーモードは「CMYK」で入稿するのがおすすめです。
ただ、必ずしも「デザイン時に指定した希望の色」になるとは限りません。出来る限り理想のイメージに近づけるためには、RGBとCMYKの特徴を知っておく必要があります。
※CMYKでデータを作成するには、Adobe社のPhotoshopやillustrator、他CMYKに対応しているソフトをご利用いただく必要がございます。
フリーソフトや、オフィスソフト(エクセル・ワード・パワーポイントなど)は対応していないものがほとんどです。
◇「RGB」の特徴
RGBは、テレビやパソコン、スマートフォン、タブレットのモニター、デジタルカメラなどのなどの映像表示方法に用いられており、1,677万7,216通りの色表現が可能です。RGBという名称は、光の三原色である「Red(レッド・赤)」「Green(グリーン・緑)」「Blue(ブルー・青)」の頭文字に由来しています。2つ以上の異なる色を混ぜ合わせることにより、別の色を作ることを「混色」といいますが、RGBでは3色の光(赤・緑・青)を混ぜて色を表現。たとえば青と赤でピンク、緑と赤で黄色となります。
この時、混ぜれば混ぜるほど明るさが加算され、色味が白に近づいていくことから「加法混色」とも呼ばれています。
◇「CMYK」の特徴
名称は、「色の三原色」である「シアン(Cyan)」「マゼンタ(Magenta)」「イエロー(Yellow)」に「ブラック(Key plate)」の頭文字をとったもの。書籍や雑誌、ポスター、絵画などの印刷で色を表わす方法で、理論上は1億400万60,401色が表現可能となりますが、実際のインクではこれほどの表現できません。また、色を重ねれば重ねるほど黒に近づくため、「減法混色」とも呼ばれています。絵具をまぜるようなイメージともいえるでしょう。
ただ、三原色(CMY)を混ぜ続けても、濁ったような暗色にしかならず、一般的に想像する黒にはなりません。そこで黒い部分をしっかり表現するために、ブラック(K)を用いるのです。
RGBとCMYKとの大きな相違は、上記のように根本的な表現方法(加法混色と減法混色)が異なるため、表現できる色域が違うという点です。色域が広いのはRGBの方で、CMYKはRGBの表現できる一部の色を再現できません。逆にRGBは、CMYKで再現できる範囲以外の色も表わすことが可能。そのため、「入校時と完成時のイメージが違う」といった問題が生じてしまうのです。
もう少しだけ、続きます!